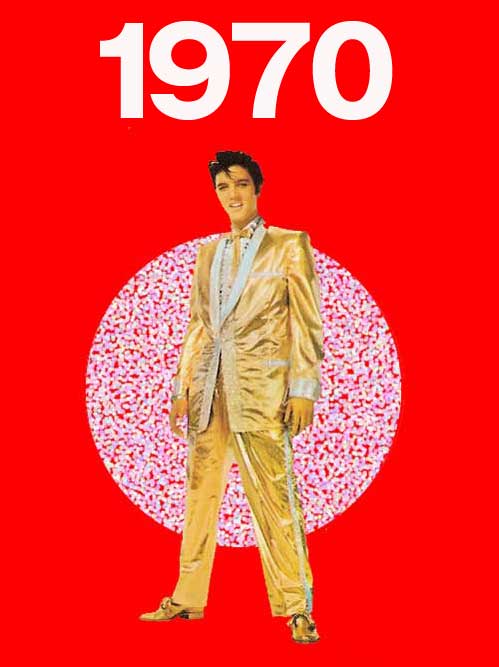
ラブ・ミー・テンダー / Love Me Tender
エルヴィス・プレスリーの登場はアメリカにとって事件でした。紛れもなくアメリカ社会を変え、さらに世界に影響を与えたミュージシャンであり、音楽ができることを実証した最初のミュージシャンです。しかし彼に特別な意図があったわけではなく、偶然のことですが、それが事件に発展したのはアメリカ社会を変えたからです。
人種差別の厳しいアメリカ南部、ワーカークラスでも最下層の生活保護を受けなければならない家庭で育った白人の若者が、どのようにして「キング・オブ・ロックンロール」に辿りついたか?あるいはなぜそうなったのか?
ラスベガスにあるヒルトン・インターナショナル・ホテルでのパフォーマンスを記録した映画「エルヴィス・オン・ステージ」に、単なる偶然ではなかった答えを見ることができます。
<ラブ・ミー・テンダー>を歌う場面があります。
エルヴィスは女性ファンにキスのサービスを始めます。ついにはスタッフの制止をふりきってホールに下りてしまい、混乱のなかをラウンドします。
自分はこのシーンが嫌いでした。多くの人が同じように「キモい」と思ってしまう場面かも知れません。でも何度も見返す内に、エルヴィスの気持ちがようやくわかったような気がするのです。
1970年「エルヴィス・オン・ステージ」の舞台となった、ヒルトン・インターナショナル・ホテルは、古いダウンタウンから離れた場所に建てられた当時話題の大型ホテルです。
いまでこそヒルトン・インターナショナルを凌駕する人気ホテルが続々と作られ、中心地が変わってしまったため、ダウンタウンと現在の中心地の狭間にあり、いまではいい場所にあるとはいえません。
ラスベガスもいまではすっかりテーマパーク化して、客層も変わりましたが、1970年はドレッシーな大人の遊び場だったラスベガスから、家族で楽しむラスベガスに変わろうとする始まりだったのです。
「すべてはエルヴィスから始まった」のフレーズは、ここでも適用されたようです。
当時、エルヴィス同様、ラスベガスでソールドアウトにできるのは、スーザン・ストラスバーグ、フランク・シナトラだけだと言われていました。しかし彼らのライブとは客層が全然違います。
「エルヴィス・オン・ステージ」の客席には、ニューヨーカーのような人は少なく、貯金を下ろして精一杯のお洒落をして、遠くからやってきた「田舎者」らしい人が多く見られます。もう二度これそうにもない人たち。
キモいと思っていたエルヴィスのキスは、その人たちの”やりくりして過ごすつつましい日常”に向けられた「頑張れよ」のキスだったと思うのです。
その暮らしが、どんなものなのか物心つく以前に五感を通して身体で知っているエルヴィスならでは共感です。
ファンサービスという表現で片付けられない人間への思い、いたわりが、派手な衣装と笑顔と女たらしなポーズに隠されたまま、何食わぬ顔で淡々と繰り広げられます。
来たこともない見たこともない自分の日常にはないゴージャスな場。
その緊張を汗と熱唱で興奮に変えることで、粉々に打ち砕き、ありのままの自分になれるように場を作り、それでも恥かしい女性の気持ちを自分が全部引き受けて、君はボクにキスしてくれないのと言わんばかりに手をさしのべる。
男ですよね、男。幸せにしてもらいたいとは願わない。ただ幸せにしたいだけ。
エルヴィスが愛された理由です。自分のことなら引っ込み思案になったけれど、人のためなら、誤解を恐れず、ただの一度も言い訳も説明もしなかったエルヴィス。
「みんなの顔を見せてくれないか」と言って客席に明かりを要求したエルヴィス。
ステージの姿をカメラに納めるのを拒否しなかった>エルヴィス。
こんなミュージシャンを見たことがありますか?
寡黙なままに行われた偉業。That's The Way It Is これこそが、「エルヴィス・プレスリーのロックンロール」なやり方だったのです。
印税生活をしていたエルヴィスにとって、RIAAの公式発表は、お金をどれだけ稼いだかということと同義語ですが、一方では「魂の救済の数」なのです。年月が過ぎて、利息を生んでいるようです。
クリスマスが近づくインディアン・サマーのような日に窓をあけて一度、エルヴィス・プレスリーを聴いてみませんか?







